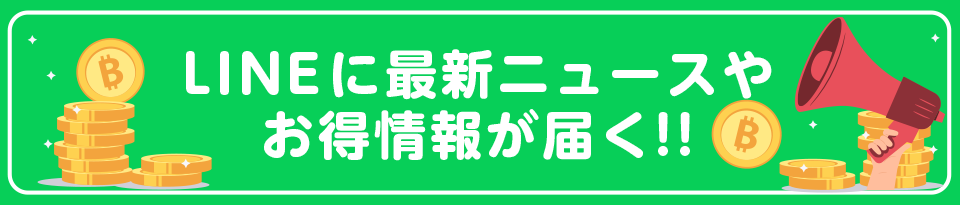Astar(ASTR)は、日本発のブロックチェーンプラットフォーム「Astar Network」で使用される基軸通貨であり、国内外で注目を集めています。
本記事では、Astarの基本情報から最新動向、将来性までをわかりやすく解説します。
- Astar Networkは2022年にローンチした日本発のスマートコントラクトプラットフォーム
- 独自のdAppステーキングモデルを採用し、開発者とASTRステーキングユーザーの双方に報酬を分配
- ソニーなど大手企業と連携し、Layer2「Soneium」導入で実需拡大を目指す
- 国内主要取引所や海外取引所で購入可能
- 価格変動や競争激化、主要ホルダー集中のリスクに注意が必要
Astar(ASTR/アスター)とは?
| トークン名 | Astar(アスター) |
|---|---|
| ティッカーシンボル | ASTR |
| トークンセクター | スマートコントラクトプラットフォーム(Layer‑1/Layer‑2対応) |
| 対応ブロックチェーン | ・Astar Network(Layer 1) ・Polkadot(パラチェーン) ・Soneium(ソニューム) ・EVM&WASM 対応マルチVM |
| 発行上限枚数 | なし |
| 現在価格 | 0.02179ドル |
| 時価総額 | 177,205,994ドル |
| 時価総額ランキング | 196位 |
| 上場済みの取引所 | Bybit・Bitget・MEXC・KuCoin・GMOコイン・bitbank・OKJ・BitTrade・Binance Japan |
Astar(ASTR / アスター)とは2022年1月にローンチした日本発のブロックチェーンである「Astar Network(アスターネットワーク)」の基軸通貨です。
開発は、日本人起業家の渡辺創太氏が率いる「Stake Technologies(ステイクテクノロジーズ)」によって主導されており、高い注目を集めています。
スマートコントラクト機能を備えた開発者向けのプラットフォームであり、分散型アプリケーション(dApps)の構築が可能です。ネットワーク内では、ASTRトークンが手数料の支払いや、ステーキング報酬、プロジェクトの意思決定に参加するガバナンストークンとして使用されています。
独自の仕組みとして「dAppステーキング(Build2Earn)」があり、dApp開発者には継続的なASTR報酬が与えられ、保有者も応援したいプロジェクトにステーキングすることでインセンティブを得ることができます。
Astar Networkは、先進的なテクノロジーと日本発という独自性を活かし、グローバルなWeb3インフラとしての成長を目指しています。
Astar Networkの歩み:主要な出来事
Astar Networkは、日本発の次世代ブロックチェーンプラットフォームとして、着実に技術開発とエコシステムの拡大を進めてきました。これまでの主要な出来事を時系列で見ていきましょう。
- 2021年9月:Plasm NetworkからAstar Networkへ改称
- 2021年12月:Polkadotパラチェーンスロット獲得(Crowdloan成功)
- 2022年1月17日:メインネット公開、Astar EVM稼働開始
- 2022年1月:約2,200万ドルの資金調達(Polychain主導)
- 2022年3月:double jump.tokyoと提携
- 2022年10月:NTTドコモと提携
- 2023年1月:「Startale Labs」設立
- 2023年9月:「Astar Tech Stack」企業向け提供開始
- 2024年2月:Astar zkEVMメインネット稼働開始
- 2024年7月:Chainlink CCIP統合、クロスチェーンに対応
- 2024年12月:オンチェーンガバナンス導入
- 2025年1月:SONY開発L2「Soneium」メインネット公開
- 2025年3月:Astar zkEVM稼働停止
- 2025年4月:ステーキング報酬体系刷新
- 2025年6月:ASTRがSuperchainERC20トークンとしてCCIP経由で本稼働
2022年のNTTドコモやdouble jump.tokyoなどとの連携は、日本国内におけるWeb3普及の重要な一歩となりました。
2023年にはStartale Labsの設立などを通じて、Astar Networkの技術基盤とエコシステムがより明確に定義され、グローバル展開の基盤が強化されました。
2024年は技術面とエコシステム拡大の年となり、Polygon Labsと提携したレイヤー2ソリューション「Astar zkEVM」のローンチや、企業連携・トークンバーンの実施、相互運用性プロトコルとの統合などが進行。さらに、Soneiumエコシステムとの連携によって、ASTRトークンの新たなユースケースが広がりました。
2025年は、Superchain対応やSoneiumでの実利用を通じて、ASTRトークンの需要と実需のさらなる拡大を目指す重要なフェーズとなっています。
ASTRのトークノミクスとホルダー分析
Astarのトークン提供モデルとホルダー構成などから、市場への影響と将来性を以下の点で考察します。
- ASTRの供給モデルと特徴
- 初期と現在のASTR配分の比較
- ASTRの総発行量と供給推移
- ASTRの上位ホルダーの構成と保有割合
Astarは2022年4月をピークとしており、その後も一時的な盛り上がりは見せつつも最高値更新にはいたっていません。市場状況を踏まえつつ、供給構造とホルダー構成を把握していきましょう。
ASTRの供給モデルと特徴
2025年7月時点での流通供給量は約81.31億ASTRとなっており、手数料支払い、ステーキング報酬、ガバナンス投票に利用されるAstar Networkのネイティブトークンとしての機能を持っています。開発者と保有者に報酬が与えられる独自の「dAppステーキング」により、供給の流動性とエコシステム内の循環が促進される特徴があります。
2024年には未使用トークンの約3.5億ASTR(全体の5%)がバーンされ、供給抑制と希少性の強化が図られました。さらに、2025年4月にはステーキング報酬体系の刷新が行われ、報酬配分の最適化とトークン発行の効率化が進められました。
このような取り組みに加え、買戻しや定期的なトークンバーンを通じて、長期的な供給抑制とトークン価値の維持が期待されています。
初期と現在のASTR配分の比較
※ グラフをタップすると各項目の詳細が表示されます。
初期配分では「ユーザー支援者+パラチェーンオークション」で全体の約52%が占められており、コミュニティとネットワーク構築に重点が置かれていました。
一方、現在は「流通中」と「ステーキング中」が全体の9割を占めており、Astar Network上での利用や保有によるインセンティブを通じて、トークンが実需ベースで機能していることがわかります。
今後、トークンの使い道が増えていくかどうかは、需要の持続に大きく関わります。特にdAppの拡大やユースケースの増加は、トークンの価値を押し上げる要因となります。ステーキングや供給の集中には注意が必要ですが、分散が進めばネットワークの安定性と信頼性にもつながります。
ASTRの総発行量と供給推移
初期には「発行上限70億枚」とされていましたが、実際にはその後のトークノミクス変更により発行上限を設けないインフレ型モデルへと移行しました。現時点での総供給量はすでに84億7,171万ASTRに達しており、過去の上限設定は実質的に撤廃されました。
ASTRトークンの供給推移は、当初の上限型モデルから、需要と参加状況に応じた「持続可能な変動型モデル」へと進化していることが明らかです。
出典:https://cryptorank.io/price/astar-network/vesting
※ グラフ上の年のラインをタップすると、各項目の詳細が表示されます。
ASTRの上位ホルダーの構成と保有割合
出典:https://astar.subscan.io/account
※ グラフをタップすると各項目の詳細が表示されます。
ASTRトークンは、上位10アカウントだけで全体の約51%を占めており、保有がやや集中しています。
最大の保有アドレスは財団が管理しているとみられますが、ロックされていない大口保有者(いわゆるクジラ)も存在しており、市場への影響には注意が必要です。今後、これらのアドレスからどのようにトークンが動くかによって、市場の流動性や価格に変化が出る可能性があります。
投資家としては、トークンの段階的リリースや流通量の変化に注目し、供給の動きを見ながら慎重に判断することが重要です。
ASTRのユースケースと注目ポイント
Astar Networkは、多様なブロックチェーンアプリケーションを支えるプラットフォームとして注目されています。ここでは、ASTRの実際の活用事例と、今後の成長を左右する重要なポイントについて解説します。
ASTRのユースケース
- ネットワーク手数料の支払い
- dAppステーキング(Build2Earn)
- ガバナンス投票
- Soneium内での決済手段
- DeFiやNFTでの活用事例
ASTRトークンの主なユースケースは、Astar Network上での取引手数料の支払い、ガバナンスへの参加(投票権)、そしてdAppステーキング(Build2Earn)による開発者支援と報酬獲得の3点に集約されます。
このような設計によって、利用者と開発者の双方にインセンティブが生まれ、ネットワークの活用が自然と広がる仕組みが形成されています。これにより、健全で持続可能なエコシステムの発展につながっています。
注目ポイント:Astar NetworkとASTRの成長を支える要素
Astar Networkは、日本発のWeb3プロジェクトであり、日本人起業家・渡辺創太氏が主導しています。Polkadotの主要パラチェーンとして、高い相互運用性とセキュリティを持ち、EVMとWASMの両方に対応することで、幅広い開発者の参加を可能にしています。
特に注目すべきは、独自のdAppステーキング(Build2Earn)モデルを通じて、開発者とトークン保有者の双方に報酬が還元される仕組みが整っている点です。これにより、ネットワークの利用が促進され、エコシステム全体の成長が加速しています。
また、トークン経済の面でも、動的なトークノミクス設計とバーン施策によって、インフレ率は約4.32%に抑えられており、持続可能なトークン経済の構築が進められています。
さらに、ソニーとの提携によるSoneium構想や、国内外の大手企業との連携(トヨタ、Microsoft、AWSなど)も注目されており、ASTRの実需とユースケース拡大が期待されています。
ASTRへの投資における3つの注意点・リスク
ASTRへの投資を検討する際は、以下の点に注意が必要です。
- 他の主要ブロックチェーンとの激しい競争
- 値動きが大きく予測困難な特性
- 外部環境への依存
Astar Networkは独自の技術やユースケースを持つものの、Ethereum(イーサリアム)やSolana(ソラナ)といった主要ブロックチェーンとの競争は熾烈です。2025年7月時点のDeFi領域でのTVL(預かり資産)シェアは全体の約0.01%と小さく、ブロックチェーン間の競争において優位性を確立するにはさらなる成長が求められます。
法定通貨と異なり、ASTRには価値を保証する中央機関が存在しないため、市場の需給バランスや投資家のセンチメントに大きく左右されます。特に、上位10アドレスで全体の約51%のトークンが保有されている現状では、大口アカウントによる売却が市場に与える影響は大きく、価格が急落するリスクも無視できません。
Astar NetworkはPolkadotのパラチェーンとして運営されており、Polkadotエコシステムの動向やガバナンス変更は、ASTRの価格や運用方針に直接的な影響を及ぼす可能性があります。また、競合ブロックチェーンの技術革新や採用状況は、開発者や投資家によるプラットフォームの選定や資金投入の判断にも関わってきます。
Astar Networkの今後の展望とASTRトークンの将来性
Astar Networkは現在、以下のロードマップに基づき、エコシステムの進化を進めています。
- Governance v1の本番導入(分散型ガバナンス体制の移行)
- ASTRのERC-7802(Superchain ERC20)対応アップグレード
- Soneiumエコシステムへの本格展開
Astar Networkは、分散型ガバナンスの導入や相互運用性の拡張、新たなLayer2「Soneium」との統合を通じて、Web3時代の基盤インフラとしての地位確立を目指しています。 特にSoneiumでは、ゲームやエンタメ領域でのユースケースを通じて、一般層へのリーチ拡大にも取り組んでおり、より幅広いユーザー層の獲得が期待されます。
さらに、ASTRトークンはdAppステーキング、ガバナンス参加、ガス代支払い、決済手段など多岐にわたるユースケースを持ち、発行上限なしという設計でありながら、トークンバーンやインフレ調整の仕組みにより、長期的な価値維持も意識された設計となっています。
さらに、日本発プロジェクトとして、ソニーやトヨタなど国内外の大手企業との連携も強化されており、実需の拡大や国際的な採用拡大に向けた足場も整いつつあります。
こうした動きを踏まえると、Astar Networkは今後の展開に注目したいプロジェクトのひとつです。中核を担うASTRトークンも、ユースケースの広がりに応じて、将来的な活用の場や価値の向上が期待されますが、今後の成長には引き続き慎重な見極めも必要でしょう。
ASTRの購入方法と取扱取引所
ASTRは、執筆時点で以下の国内取引所と海外取引所での購入が可能です。
- GMOコイン:高いセキュリティと信頼性、取引ツールが充実
- bitbank:アルトコイン取引量が国内最大級、堅牢なセキュリティ体制
- BitTrade:豊富な銘柄と手数料無料の取引が特徴
- OKJ:シンプルなUIと狭いスプレッドが魅力
- Binance Japan:グローバル最大手Binanceの日本法人
上記の国内仮想通貨取引所では、口座開設後すぐにASTRの購入が可能です。
- 国内仮想通貨取引所の口座開設
- 日本円を入金
- ASTRを購入
公式サイト:https://coin.z.com/jp/
上記のような海外仮想通貨取引所でASTRを購入するには、まず国内取引所で元手となる仮想通貨を準備する必要があります。具体的な流れは以下のとおりです。
- 国内仮想通貨取引所の口座開設
- 国内仮想通貨取引所へ日本円を入金
- 元手となる通貨(BTCやETHなど)を購入
- 海外仮想通貨取引所の口座を開設
- 国内取引所から海外取引所へ元手通貨を送金
- 元手通貨でUSDT(Tether)を購入
- USDTでAstar(ASTR)を購入
以上のステップを踏むことで、海外仮想通貨取引所でASTRを購入できます。購入を検討している方は、ぜひ上記の手順を参考にしてみてください。
【新規口座開設特典】
\ 最大6,200ドルのボーナス&クーポン /
関連:Bitget(ビットゲット)キャンペーン総まとめ
関連:Bitgetの評判と安全性は?口コミやメリット、デメリットを解説
まとめ
Astar Networkは、日本発の先進的なスマートコントラクトプラットフォームであり、Polkadotのパラチェーンとして高い技術力と相互運用性を誇ります。独自のdAppステーキングモデルにより、開発者とトークン保有者の双方に報酬を還元し、エコシステム全体の成長を促進しています。
ソニーをはじめとする大手企業との連携も進んでおり、Web3の実需拡大、特にゲームやエンタメ領域での応用が期待されています。一方で、競争激化や価格変動、主要ホルダーへのトークン集中といったリスクも存在します。
今後は、Layer2技術の実用化とユースケース拡大が、持続的な成長の鍵となるでしょう。ASTRへの投資を検討する際は、供給動向や市場環境をよく理解したうえで、慎重に判断することが重要です。